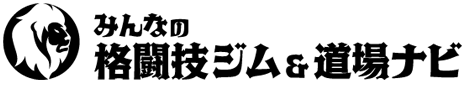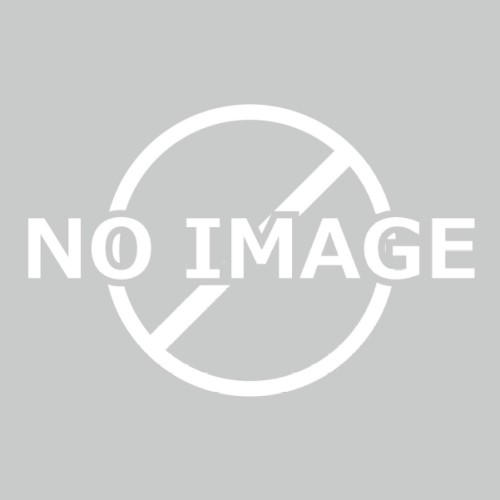格闘家 / 指導者 インタビュー
柔道家【昭道館浅見道場】土屋文夫(つちやふみお)さん

Table of Contents
今回のゲスト 柔道家【昭道館浅見道場館長】土屋文夫さん
埼玉県入間市にある浅見道場。
昭和62年4月に開設され、今年2023年で35年の歴史を迎えます。
常に「基本で忠実な正しい柔道」を指導してきた土屋文夫さん。
これまでの門下生は、全国中学校大会でベスト8の他、インターハイ3位、全国高校柔道選手権大会3位、全国選技体重選手権大会、全日本女子柔道選手権大会3位など、数々の実績を残し続けています。
土屋さんご自身も、早稲田実業中学校時代から柔道を始め、高校では都で団体ベスト8、大学時には東京学生、全日本学生優勝大会や国体でもご活躍され、柔道7段の実力者です。
大学卒業後には地域に貢献したいと、接骨院と柔道指導者の道へ。
現在まで35年間、道場で子ども達を中心に指導を行い、全日本柔道連盟によるBライセンス審判員・Bライセンス指導員としてもご活躍されています。
「先生はすごく優しいけど、ときどきこわいです」
と、小学生の子供たちに慕われる土屋さんにインタビューをしました。
――柔道を始めたきっかけは?
子どもの頃は野球好きでしたが、当時の野球は大人気で早稲田実業(中学校)入学時には同学年の男子120名くらいが野球部に入部し、卒業時には13名しか残らなかったと思います。それくらい厳しいのですよね。
私は中学2年生まで、英語部に入っていました。
体格が良かったせいか、英語の先生に「柔道をやってみたら」と勧められ、途中から柔道部に入部したんです。
早稲田実業はスポーツが盛んな学校なので、先生も見込みがありそうな生徒がいると積極的に推してくださりました。
――学生時代に柔道をやめたいと思ったことはありましたか?

学校から徒歩10分の場所に早稲田大学の道場があり、高校生や大学生と一緒に稽古をしていた厳しい時期がありました。
先輩達は体格も大きいですから、力も上で、練習に付いていくのが大変でした。
今とは違い、練習中は水も飲めない、トイレも行けない雰囲気でしたね。
その中で、投げられたり、絞められたりと稽古中は辛かったです。
ですが、やめたいと思ったのはその時期だけで、その後は一度も思ったことはないです。
――心に残っている試合を教えてください。
大学時代に東京学生、全日本学生優勝大会の代表決定戦で、東京教育大学(現筑波大学)の山藤選手との試合です。
山藤選手は私よりも大きく、絶対に勝てない、すぐに投げられてしまうと感じましたが、
「どうせ負けるなら当たって砕けろ!」
と思い切って、戦いに挑みました。
結果は、場外「注意」で僅差負け。
悔しい思いもありましたが、その時の自分ができる精一杯の試合をしたんだと達成感がありました。
最後まで戦ったことを誇らしく思いましたね。
今でも忘れられない試合です。
――柔道を始めて良かったこと、魅力、人生の役に立ったことを教えてください。
柔道を始めて、まず性格が変わりました。
当時の私は三男坊で、わがままで自分勝手なところがありました。
柔道に出会えたことで相手を思いやる気持ちが生まれ、人として成長できたと感じます。
特に、大学時代の恩師から「人に対する感謝の気持ち」を教えいただきました。
柔道は相手があって稽古ができ、試合が成立する競技です。
ですから挨拶1つも、相手に対する感謝の気持ちを表しています。
あと、たとえ辛いことがあっても
「あの苦しい稽古に耐えてこられた自分だから大丈夫」
と、強い気持ちを持つことができました。
柔道を通じて、たくさんの人と人とのご縁が繋がったことが人生に大きく影響しています。
――接骨院と併設して道場を開設した経緯についてお聞きしたいです。
大学生の頃、卒業したら一般企業に勤めて会社員になるつもりでした。
でも就職活動を考え始めた頃、当時立教大学の小野沢昭雄先生に
「仕事をするだけでなく、地域に貢献できることをやれ」
と、アドバイスをいただき、その言葉が心に残りました。
しかし、「自分は大した実績もないのに、人に指導していいのだろうか…」と思いましたね。
でも「せっかく柔道をやってきたのだから接骨院を開いて道場もやろう!」と早めに決断しました。
小野沢先生からは柔道整復師の学校を紹介していただき、卒業後は2年間大東医専に通って柔道整復師の資格を取得しました。
その後は、9年間見習いで市内の病院の整形外科に修業で働く傍ら、小島道場という道場で柔道の指導を行いました。
昭和62年4月に接骨院を開業して、半年後には道場も完成、小島道場から門下生25名を引き継いでスタートしました。
今よりも子ども達が大勢通ってきて、5歳の小さい子から社会人まで来て盛り上がりましたね。
「練習はきついだけではだめ。トレーニングには遊びも取り入れる方がいいと」
と国際武道大学の春日俊先生から助言に受け、ときどき練習の合間にサッカーやスケートリンクで滑るなど、柔道以外のスポーツを一緒に行い、
練習が単調で毎日同じことの繰り返しとなって飽きてしまわないように工夫をしてきました。
――指導者として心がけていることがはありますか。

門下生には怪我をさせないこと、挨拶をすることを意識しています。
大事なことは「基本に忠実な柔道」を教えること。
正しく組んで、力を出し切る稽古をすることで、試合に出ることや優勝を目指す目標が見えてくるように指導しています。
上級生が下級生を投げる時も、怪我をさせないことや、受け身が取れるような投げ方をすることも伝えています。
柔道は学校の体育の授業でも行っていますが、授業中の事故が問題になることがあります。
やはり相手を思い、うまい投げ方を丁寧に指導しないと怪我を起こしやすくなります。
それには基本に忠実になり毎日の練習を欠かせず、繰り返さないと身につけられません。
――浅見道場は女子の門下生も多いように感じます。
最近は、女子でも男の兄弟が先にやっているのをみて「私も柔道をする!」と習いにくる子が増えました。
オリンピックの年には選手の活躍に影響されて、入門してくる子もいます。
特に女子は自分でやりたいと思って入るくらいですから、気持ちも強いですね。
逆に男子になると、お母さん達が連れてきて「うちの子は鍛えたほういいと思って」「精神面が強くなってほしい」と言われて、渋々来る子もいます。
どんなことでもそうですが、柔道はコツコツ努力をすればみんなできるようになります。
確かに運動神経が優れていて、センスがいいなと思う門下生もいますが、すぐに成果を出せなくても続けることが大切です。
中には「勝てばいい!」という考えを持っているご家庭がありますが、今すぐ勝てなくてもいいのです。
その場の結果だけを見て、すぐに諦めなくても大丈夫です。
一喜一憂せず、長い目で見てあげてほしいと思います。
練習を積み重ねていれば、いずれ勝てる日が来るかも知れないので見守ってあげてくださいね。
彼らには竹のように真っ直ぐ育ってほしいと思っています。
そして、柔道だけでなく、文武両道で勉強にも励んでもらいたいですね。
門下生の貴重な子ども時代をそばで見れて、共に成長を喜べることが楽しいです。
――これから柔道を始める人へメッセージをお願いいたします。

継続は力なり。
どんなことでも、止めないで続けることが大切だと思います。
天才の99%は努力と言われています。
自分に何ができて、何が足りないのかをよく考えて稽古をすれば伸びて行きますので、ぜひ挑戦してみてください。
――お休みの日は何をされてお過ごしでしょうか。
ドライブに行ったり、外食をしたり自宅でのんびり過ごします。
でも日曜日は柔道の行事、昇段昇級審査会で出かけることが多いです。
――憧れのアスリートや尊敬している人はいらっしゃいますか。
大学時代の恩師、柔道10段の大澤 慶巳先生、9段の小野澤 弘史先生です。
「正しく組んで、正しく技を覚えろ」
とお二方の先生には何度も言われて、今の浅見道場での指導も先生方の教えを受け継いでいます。
厳しい方でしたが、人に感謝することや礼儀を背中で見せていただき、実際に稽古も付けてもらいました。
学生時代は恐くてとても話せませんでしたが、大人になるとお会いして話ができるようになり、とても良い先生でした。
もう1人は、1964年東京オリンピック金メダル岡野功先生です。
岡野先生は、技を掛けなければ投げられ、技を掛ければ返される、立っていることができなかったくらい、すごく強かったですね。
どの先生も私に人として大切なことを教えてくださいました。
――座右の銘やモットーがあれば教えていただけますでしょうか。

我が、浅見道場の道場訓です。
「一期一会」
人と人の出会いを大切にしてほしい。
「変化の妙」
恩師、大澤 慶巳先生の教え。一つの技だけでなく、柔軟に、型を変えて相手に挑む。
「日々の精進」
毎日努力と積み重ねで頑張ること。
――今後の目標があれば教えてださい。
私は柔道のおかげで、良い先生や友達に出会いから多くのこと学びました。
今、振り返っても、続けてきて良かったと思っています。
柔道の道場から大勢の門下生が旅立ち、大人になりました。
今でもときどき、当時教えていた門下生が遊びにきたり、連絡をくれます。
開所したときから、いずれ彼らが大人になり、社会人や親になっても、いつでも道場に遊びに来られるようにと思っています。
微力ではありますが、これからも柔道を通して恩返しがしたいと思っています。
土屋さん、この度はお忙しい中ご協力いただき本当にありがとうございました!
おわりに
土屋文夫さんが代表を務める浅見道場は、入間市の東町で浅見接骨院と併設されています。
長年柔道愛に熱い土屋さんから指導いただける貴重な体験が得られますので、お近くにお住まいの方、ぜひ足を運んでみてくださいね!
住所 埼玉県入間市東町7-14-8
TEL 04-2964-4820
E-mail: asami-sj@ictv.ne.jp
<インタビュー&記事執筆:飯塚 まりな>
ライター・イラストレーター
インタビューを中心に活動中。
Web、フリーペーパー、書籍を執筆。
ほんわかしたイラストを描く。